院長のひとり言
低温期が長いのは何故?
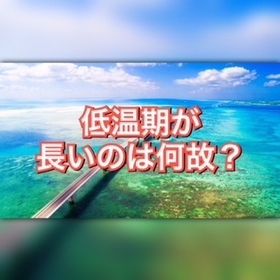
低温期が長いのは何故?って疑問を持った事ありますよね。
妊活をしている人の多くは基礎体温ってつけていると思います。
今回は低温期が長い状態の時に体の中でどんな事が起こっているのか、低温期が長いと妊娠に影響はあるのかどうかという事をお伝えしますね。
実際、人によって低温期や高温期の長い短いなどサイクルの違いってあるんですよね。
低温期の日数には個人差はあるんですけど、一般的な生理周期である28日を基準にすると、14日程度が理想日数と言えるかもしれませんね。
ただ、あくまでも目安であって、それより1~2日程度長いときや短いといった多少の誤差なら、とくに心配ないですよ。
それ以上に低温期が長いという方のほとんどは、排卵の遅れによるものが考えられるんです。
基礎体温は排卵時期前後から高温へと移行しますよね。
そのため、排卵が遅れると低温期の日数が延びるという事になりますよね。
低温期が長くなる理由としては卵胞や卵子を作る働きを持っている卵巣の働きが低下している事が考えられす。
僕が施術をしている時も変化が見られなく、低温期が1ヶ月程度続くようなサイクルが繰り返されしまう場合は卵巣機能の低下を疑うんです。
高温期がなかったり、短かかったり、低温期と高温期の差が小さい場合は無排卵の可能性も考慮しています。
無排卵月経の場合も、低温期が長いという特徴が見られるんで、排卵が行われていない可能性があるんです。
これらは卵巣機能の低下やエストロゲン不足によって卵胞の発育が遅いという事がわかります。
排卵がスムーズにいかない、または無排卵の状態では、排卵によって多く分泌されるはずのプロゲステロンも分泌されません。
プロゲステロンは高温期を維持し、妊娠しやすい子宮環境を整えてくれるホルモンです。
卵の発育遅延や無排卵の状態ではプロゲステロンが分泌されないため、なかなか高温期に移行せず低温期が続く原因となるんです。
卵巣の働きが低下する原因としてはストレスや生活習慣の変化があり、卵巣機能の低下により排卵されないという事が起こってきます。
また、冷えなどによる血行不良によって子宮や卵巣の血流も不足してしまい、卵胞の発育が遅くなります。
卵胞の発育が遅いと低温期が長くなり、生理開始日から排卵するまでに時間がかかるんです。
実は夜更かしなども卵巣の働きを低下させる原因になると考えられますよ。
一般的に卵胞や卵子は夜中に成長するとされています。
夜遅くまで起きていると卵胞や卵子を育てるために必要な血液が、卵巣へ十分に運ばれませんから、卵巣機能の低下が疑われます。
生理周期を整える為にまずは低温期を正常化していく事が必要かもしれませんね。
卵巣機能を向上させる為にも生活習慣の見直しは必須です。
毎日、運動はしていますか?
食事は質の良いものをバランスよく、添加物を取らないように意識していますか?
睡眠時間は確保できていますか?
是非、参考にしてもらえると嬉しいです。
iPhoneから送信
カテゴリ
- 妊活 (62)
- 妊活先生YouTube (28)
- 妊活のポイント (16)
- 不妊 (7)
- 腸内環境 (1)
- セックスレス (2)
- 会陰切開 (1)
- 帝王切開 (1)
- 陰陽論 (1)
- 腎 (2)
- 卵子 (1)
- 性欲 (1)
- 生理関係 (6)
- マタニティ (1)
- 逆子 (1)
- 産後の骨盤矯正 (3)
- 内臓と顔の関係 (1)
- エイジングケアと鍼灸 (1)
- 乾燥肌を防ぐ生活習慣 (1)
- 美容意識とお悩み (1)
- ホルモンと美容 (3)
- 40歳からのホルモンバランス (1)
- アディポネクチン (1)
- 活性酸素の体への影響 (1)
- 睡眠と美肌 (1)
- 糖質と体 (4)
- 糖化 (1)
- 内臓と美肌 (3)
- 肝臓 (1)
- 冷えと美容 (4)
- 美容と血液 (4)
- オ血と運動 (1)
- 陰陽の食材 (2)
- スキンケア (2)
- 食事と美肌 (4)
- 陰陽の食材 (2)
