院長のひとり言
妊活を中医学的視点から考える〜高プロラクチン血症〜
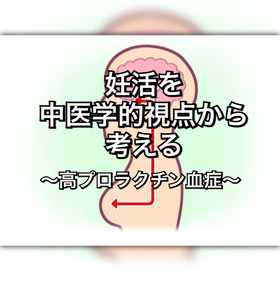
不妊の原因にもなる高プロラクチン血症を中医学から考察してみたいと思います。
プロラクチンとは母乳を作り、分泌するホルモンです。
母乳に関わるホルモンですので本来は出産後、赤ちゃんに母乳を与える時に多く放出されるものですよね。
出産後の授乳期には排卵・月経がしばらく起こらない期間がありますが、これもプロラクチンが関係してして、排卵を抑えることで妊娠を防ぐ効果もあるんです。
しかし、授乳すべき時期以外にプロラクチンが多く分泌されると乳中が出るだけではなく、排卵が抑えられて月経停止や無排卵などの生理不順、流産を引き起こしてしまう事から不妊の原因となってしまうんです。
中医学では、おっぱいは肝と非常に関係があります。
特に乳頭は肝の通り道になっている場所です。
肝の通り道が古い血液や汚れた水で塞がれた状態が高プロラクチン血症と考えることもできるんです。
肝の通り道が塞がれる原因は大きく分けると3つ。
1.肝鬱血瘀(かんうつけつお)= ストレスにより肝の通り道が塞がる。
2.肝腎不足(かんじんふそく)= 元々の血が少なくて流れが悪くなり、肝の通り道が塞がる。
3.脾虚痰阻(ひきょたんそ)= 胃腸での水分代謝がうまくいがず、汚れた水が溜まり、肝の通り道が塞がる。
1つの要因だけでなく、多くの方が2つ以上の要因が関係しています。
直接的な原因としてはストレスが関係している事が多いように感じます。
肝に血が少ないとストレスに弱くなります。
肝や脾は臓腑と生理機能の関係から特に精神的なストレスの影響を受けやすいため、注意が必要です。
また、肝は全身の気の巡りを統括していて、自律神経をコントロールして情緒の安定を助けています。
ストレスによって肝に異常が起こると、自律神経のバランスが乱れイライラしやすくなってしまったり、気逆の症状や気の巡りが悪くなり鬱々とするといった気滞の症状が現れます。
また、プロラクチンは腎の働きによるものとも考えていきます。
中医学での腎は生命に関わる部分です。
プロラクチンを分泌する下垂体前葉は脳の一部。
脳は髄海と呼ばれ、髄海を主るのは腎なんです。
排卵が無いということは、この余った腎精を合わせて子どもを作るということができないということです。
腎精を消耗し過ぎて、もしくは補うことができず、充足していない可能性があり、これを腎虚と言っています。
腎が虚する原因に過労、冷たい所での立ち仕事・ストレス、寝不足、栄養失調、塩分(化学調味料)を過剰に長期間摂取、ホルモン療法など、様々な身体的、精神的な要因が関係してきます。
最近ではスマホやパソコンが普及し、子どものうちから目を酷使した生活をしているため、腎精が充実するよりも消耗が激しいようにも感じます。
そして最後は脾の症状。
妊活をしていると考えることが膨大に増え、脾が大量の血を必要とします。
脾の持っている精気は意と智と呼ばれ、記憶力や思考力に関係する気になります。
脾は飲食物を消化吸収し、気血津液を作り出す原動力となると言われています。
この脾が働かなくなると、血が足りなくなり精神活動、体のあらゆる指令を出している心に血が行かなくなり、精神的にバランスを崩していきます。
胃腸が弱いタイプの方は基礎体力も低下気味ですので、やはりストレスに強いとはいえません。
腎と脾はそれぞれ、先天の気(腎)と後天の気(脾)と呼ばれ、生命維持に必要な気になります。
つまり、根本的に胃腸が弱かったり、代謝が落ちている方は必然的にストレスの影響を受けやすく肝、腎の状態を悪くしやすいんです。
そのような状況が続いてしまっている事でホルモンのバランスを崩す事で高プロラクチンの状態を引き起こしていると考えられます。
妊活を負担に感じたり、気持ちは大丈夫と思っていても身体に出てしまっている事も多いんですよ。
妊活は体質を改善し、卵子の質を向上させる事が目的となりますが、体全体をよくして行く後が最終的に良い卵子を育てる事につながっていきます。
卵子も細胞の1つ。
そして、体は細胞の集合体です。
体を根本的に変えるために子宮や卵巣だけにフォーカスし過ぎる事なく、体質改善をすすめてもらいたいと思います。
参考になれば嬉しいです。
iPhoneから送信
カテゴリ
- 妊活 (62)
- 妊活先生YouTube (28)
- 妊活のポイント (16)
- 不妊 (7)
- 腸内環境 (1)
- セックスレス (2)
- 会陰切開 (1)
- 帝王切開 (1)
- 陰陽論 (1)
- 腎 (2)
- 卵子 (1)
- 性欲 (1)
- 生理関係 (6)
- マタニティ (1)
- 逆子 (1)
- 産後の骨盤矯正 (3)
- 内臓と顔の関係 (1)
- エイジングケアと鍼灸 (1)
- 乾燥肌を防ぐ生活習慣 (1)
- 美容意識とお悩み (1)
- ホルモンと美容 (3)
- 40歳からのホルモンバランス (1)
- アディポネクチン (1)
- 活性酸素の体への影響 (1)
- 睡眠と美肌 (1)
- 糖質と体 (4)
- 糖化 (1)
- 内臓と美肌 (3)
- 肝臓 (1)
- 冷えと美容 (4)
- 美容と血液 (4)
- オ血と運動 (1)
- 陰陽の食材 (2)
- スキンケア (2)
- 食事と美肌 (4)
- 陰陽の食材 (2)
