院長のひとり言
遺残卵胞と調整周期
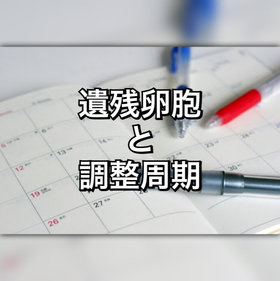
体外受精を受ける為に採卵した後はソフィアAやプラノバールなどのピルを処方されることがあります。
これって何のためなの?って思った事ありませんか?
自然な妊娠では卵胞は1個しか育ちません。
しかし、体外受精ではホルモン剤を使用して卵巣に数個の卵胞をつくらせて大きく育ったものを採卵します。
その過程で、どうしてもとりきれない卵がでてきてしまうんです。
仮に目視で小さいものまで全て根こそぎ採卵したとしても目で見える範囲ですし、ホルモン剤は少なからず全ての卵胞に影響を与えています。
採卵後の卵胞は黄体へと変化していきますが、クロミッドを服用していた周期では黄体になった卵胞以外の小さな卵胞にもホルモン剤の影響が残っています。
この卵胞が次周期にFSHの作用を受けて中途半端に成長していく事があり、これを遺残卵胞といいます。
遺残卵胞があると新しい卵胞の成長を妨げてしまうほか、成長したでも空砲、受精機能のない卵胞の可能性が高いため、遺残卵胞が消えるまで体外受精を見送ることが多くなります。
遺残卵胞は黄体ホルモンが十分にないことが理由の1つとも言われています。
採卵後の卵胞は黄体に変化し、黄体からはエストロゲンとプロゲステロンというホルモン分泌されています。
採卵後に処方されるソフィアAはプロゲステロンとエストロゲンの混合薬になるんです。
その為、採卵後にソフィアAを服用する事でプロゲステロンとエストロゲンを直接補充することにより、本来の黄体から出ているよりも多くのプロゲステロン・エストロゲンの量となります。
そうすると脳は黄体ホルモンが充分にあると判断し、下垂体からのFSH・LHの分泌を抑制します。
FSHやLHが出ないければ卵胞は育ちませんから結果的にクロミッドの影響で黄体期に残っていたその他の卵胞も、FSHが抑えられる分、育つことができなくなり退縮するんです。
排卵を一時的に抑制すれば、遺残卵胞ができる確率も下がりますし、卵巣を休ませることで少し乱れた卵巣の機能や状態がより良い方へ回復する手助けをするということではないかということですね。
遺残卵胞は排卵誘発剤を使った周期に起こりやすいとされていますが、すべてが解明されているわけではなく、なぜ遺残卵胞ができてしまうのかは、いまだはっきりとは分かっていません。
不妊治療は長くなればなるほど、様々な薬を服用したり、注射や処置を行ったりすることで体にも負担がかかっています。
もともと卵巣機能が低下している場合は排卵誘発剤の後、ホルモンのアンバランスを起こしやすい傾向にもあるんです。
通常は1〜2周期でもとに戻りますが機能低下が著しいとアンバランスなままでいずれ閉経なんて事にもなってしまいます。
不妊治療を行っていると毎月の排卵や卵胞の数、さまざまな治療のタイミングなどが大切になります。
そのため1周期治療を見送るとなると、焦りを感じてしまう方もいらっしゃると思います。
けれど、体のバランスを整える事は結果的に良い卵子を育てる事につながります。
焦らずに次の周期にベストな状態で挑めるように体質改善をしっかり意識して下さい。
体外受精を受ける際は多少のホルモン補充は仕方のない部分ですが、極力少なくした方がいいですよね。
ただ、体質改善が進んでいれば体が自分で微調整はしてくれるように働きますから、病院任せにせずに体質改善をする事で少しずつでもご自身の妊娠力、自己治癒力を高める努力をして下さいね。
参考になれば嬉しいです。
iPhoneから送信
カテゴリ
- 妊活 (62)
- 妊活先生YouTube (28)
- 妊活のポイント (16)
- 不妊 (7)
- 腸内環境 (1)
- セックスレス (2)
- 会陰切開 (1)
- 帝王切開 (1)
- 陰陽論 (1)
- 腎 (2)
- 卵子 (1)
- 性欲 (1)
- 生理関係 (6)
- マタニティ (1)
- 逆子 (1)
- 産後の骨盤矯正 (3)
- 内臓と顔の関係 (1)
- エイジングケアと鍼灸 (1)
- 乾燥肌を防ぐ生活習慣 (1)
- 美容意識とお悩み (1)
- ホルモンと美容 (3)
- 40歳からのホルモンバランス (1)
- アディポネクチン (1)
- 活性酸素の体への影響 (1)
- 睡眠と美肌 (1)
- 糖質と体 (4)
- 糖化 (1)
- 内臓と美肌 (3)
- 肝臓 (1)
- 冷えと美容 (4)
- 美容と血液 (4)
- オ血と運動 (1)
- 陰陽の食材 (2)
- スキンケア (2)
- 食事と美肌 (4)
- 陰陽の食材 (2)
