院長のひとり言
睡眠不足は多嚢胞性卵巣を引き起こす
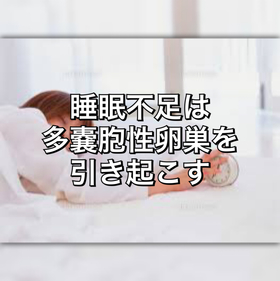
毎日しっかり寝てますか?
不妊治療をしている人、妊活をしている人でもフルタイムで働いていたりで睡眠時間が短くなっている人も多いように感じます。
実は不妊の原因の1つでもある多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)にも睡眠不足は大きく関係しています。
多嚢胞性卵巣になってしまう要因の1つであるインスリン抵抗性は、長期間に渡る糖分、主に砂糖のとりすぎが原因ですが、睡眠不足だと血糖値のコントロールが難しくなる為に発症頻度が高くなってしまうんです。
睡眠と血糖値の関係でポイントとなるのがメラトニンの分泌不足。
メラトニンは睡眠サイクルを司るホルモンで、夜間に高く日中に低いというリズムを作りだしていて、脳の松果体から分泌されています。
メラトニン自体はインシュリン分泌を抑制する効果があり、血糖値を調節するインスリンの分泌をコントロールしています。
メラトニン分泌がうまくいかないと血糖値の調整ができなくなり、多嚢胞性卵巣を引き起こしやすくなると言えるんです。
通常、排卵には脳にある下垂体から分泌されるLH(黄体ホルモン)とFSH(卵胞刺激ホルモン)という2つのホルモンが関わっています。
PCOSの方はこのバランスが崩れて、LHばかりが過剰分泌されることによって、排卵がうまく行われなくなるんです。
また血糖値を下げるホルモンであるインスリンもPCOSに関連しており、インスリン抵抗性(高インスリン血症)があると、局所的に卵巣内の男性ホルモン量が増加します。
男性ホルモンは卵胞の発育を抑制し、卵巣の外側の膜(白膜)を厚くすることによって排卵を妨げてしまうんです。
病院ではインスリン抵抗性がある方には、糖尿病の薬であるメトフォルミン(メルビンなど)が処方されるようです。
このメトフォルミンは排卵障害を改善することがわかってきています。
糖尿病の薬は血糖を下げてインスリンの過剰な分泌を抑えるので、卵巣で男性ホルモンも抑えられ、卵巣内のホルモン環境が改善され、排卵しやすくなると考えられているんです。
PCOSは5~10%の女性にみられると言われていますが、同時に睡眠障害の方に多いことが知られています。
PCOSの方はBMIとは無関係に睡眠性無呼吸を起こしやすいとも言われています。
睡眠に関係しているメラトニンは睡眠を司るだけでなく、活性酸素を抑制する抗酸化作用を有することが知られています。
排卵過程において、酸化ストレスが生ずると卵の成熟を妨げてしまうんです。
それをメラトニンが卵胞内で抗酸化物質として働き、卵を保護しているというわけです。
メラトニンの抗酸化作用は卵胞液中で卵を守っていると考えられ、実際にメラトニンを摂取することで、受精率や妊娠率がよくなることも確認できているそうです。
睡眠時間を確保する事で、PCOSを予防、改善する事もできるという事なんですね。
現代人の多くが睡眠不足だと言われています。
しかも日本人の女性は世界一睡眠時間が短いと言うデータもあります。
睡眠時間と不妊の関係って意外とバカにできないんですよ。
参考になれば嬉しいです。
iPhoneから送信
カテゴリ
- 妊活 (62)
- 妊活先生YouTube (28)
- 妊活のポイント (16)
- 不妊 (7)
- 腸内環境 (1)
- セックスレス (2)
- 会陰切開 (1)
- 帝王切開 (1)
- 陰陽論 (1)
- 腎 (2)
- 卵子 (1)
- 性欲 (1)
- 生理関係 (6)
- マタニティ (1)
- 逆子 (1)
- 産後の骨盤矯正 (3)
- 内臓と顔の関係 (1)
- エイジングケアと鍼灸 (1)
- 乾燥肌を防ぐ生活習慣 (1)
- 美容意識とお悩み (1)
- ホルモンと美容 (3)
- 40歳からのホルモンバランス (1)
- アディポネクチン (1)
- 活性酸素の体への影響 (1)
- 睡眠と美肌 (1)
- 糖質と体 (4)
- 糖化 (1)
- 内臓と美肌 (3)
- 肝臓 (1)
- 冷えと美容 (4)
- 美容と血液 (4)
- オ血と運動 (1)
- 陰陽の食材 (2)
- スキンケア (2)
- 食事と美肌 (4)
- 陰陽の食材 (2)
